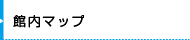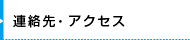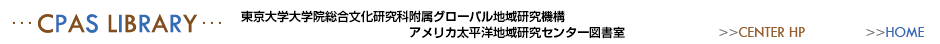

図書紹介新着図書紹介
このページでは、CPAS所属教員が新着図書の一部を定期的に紹介していきます。
Jill Lepore, Book of Ages: The Life and Opinions of Jane Franklin
–––– New York: Knopf, 2013 アメリカを代表する人物として取り上げられることの多いベンジャミン・フランクリンに仲の良い妹があり、生涯を通じて彼と密に手紙をやりとりしていたことは、少数の専門家を除いて知られていない。 フランクリン自身も兄ジェイムズの印刷所で徒弟修業したことをきっかけに書くことを独学で学んだが、妹のジェーン・ミーコム(15歳で結婚)は、職人階層の出自に加えて女性であるがゆえに、学ぶ機会をなおさら得られなかった。 著者はその彼女が自分のスペリングなどの誤りを気にしながらフィラデルフィアの、またイギリス・フランス滞在中の兄に送った数多くの書簡を読み込み、18世紀女性史研究につきまとう、史料が質・量共に限られるという壁を部分的に突き崩している。 著者の描くフランクリンの妹は、兄との率直な対話を心から大事にした、闊達な女性である。 ジェーン・ミーコムは度重なる出産、職人である夫や子供が身体や精神の病を発症したのにくじけず、長期滞在者向けの宿を営み、後には複数の孫の面倒も見ながら83歳の長寿を全うした。 彼女はフランクリンの印刷物や著作を熱心に読んで、彼女への支援を惜しまなかった兄に感謝しつつも、その宗教観を批判するなどフランクリンと対話し続けた。ジェーンが革命戦争の中、書簡中に政治的な意見を記すようになり、 老境にあっては貧しい者が学ぶことがいかに構造的に困難であるか兄に伝えたことは、読者に感銘を与えるだろう。また、印刷業の修行を受けたものの自己規律に欠けて成功がおぼつかなかったジェーンの息子の一人を支えようと、 フランクリンが有名なエッセイ「富に至る道」の印刷の仕事を与えた、という解釈は、読者のフランクリン像にも影響を及ぼすはずである。(橋川健竜)<2015年> 目録情報 John Hirst, Australian History in Seven Questions
–––– Collingwood, Vic.: Black Inc., 2014 本書ではオーストラリア政治史の碩学が、ニューサウスウェールズ植民地への入植開始以来20世紀末までの歴史を、「なぜ囚人植民地が平和裏に民主政社会に変貌したのか」「オーストラリア植民地はなぜ連邦を結成したか」 「なぜ戦後の移民プログラムは成功したのか」など、7つの問いに対する解答の形で論じている。アボリジナルが農業を営まなかった理由を考古学などを援用して論じる第1章を除き、扱われるのはいずれもオーストラリア政治史の重要問題である。 本書の魅力は、著者が長年の研究のエッセンスを惜しげなく提供していることにある。 流刑植民地という言葉と、囚人たちが作り上げた植民地という実態のズレの指摘などはその最たるものであり、オーストラリア社会の個性を感じさせる。 連邦結成のエネルギーを経済利害や人種主義に求めず、オーストラリアは外敵もなく民族や宗教をめぐる深刻な対立もない平和な社会だ、という同時代人の心情に求める解釈(彼らがアボリジナルの排除を無視していたことを、著者は指摘している)や、 連邦結成という公的・制度的な枠組みづくりより、ブリテン帝国の戦争への派兵のほうが国民統合の基盤としてはずっと力を発揮したという論点も、ナショナリズムを研究対象にしたい人は一読の価値がある。 史実の知識がある読者はもちろん初学者も、創意に富んだ一国史がどう構想されるかを追体験できる。著者がオーストラリアをイギリス、北米やアルゼンチンなどと積極的に比較しているのも興味深い。 オーストラリア史研究を目指す読者は本書を、著者の専門的な業績へと読み進むための一助にできるだろう。(橋川健竜)<2015年> 目録情報 Martin Lyons and Penny Russell, eds., Australia's History: Themes and Debates
–––– Sydney: University of New South Wales Press, 2005 オーストラリア史学会の後援のもとで編まれた本書は、オーストラリア史を専攻したい学生の基本書である。10名の代表的研究者が、21世紀初頭の時点でオーストラリアをどの研究書の示唆のもと、 いかなる視点で眺められるかを提案している。本書の特色は、自国史を時期ごとに輪切りにして論じるのではなく、むしろ、定番的な通史・政治史から意図的に離れて問いを立てていることだ。 最初の章は先住民史の研究動向の変遷をたどり、なぜアボリジナルの歴史が本書の刊行当時、深刻な政治的論争を招いていたかを論じる。 続いてオーストラリアの過去を北(18世紀前半以来の、現インドネシアなどの島々との交易・移動)から、また西(西オーストラリア州)から考える、さらに日本や中国を含めたアジア諸国との関係を考えるといった、 「東から・南から」でない柔軟な空間理解を提唱する章が並び、いずれも200年、300年といった期間を扱う。「国民性」や「本国イギリスと(元)植民地オーストラリアの関係・比較」などの伝統的な論点は、入植者社会論、 移民受け入れの法的・社会的態勢、20世紀における市民権のあり方、戦争とオーストラリア社会、都市と郊外、を扱う各章へと組み換えされている。各章の註を確認すれば重要文献の書誌情報を得られるので、 自分の関心に近い章だけ読んでも初学者には大いに役に立つ。しかしその上で、ぜひ通読もしてもらいたいと思う。刊行後の研究動向については読者が別途補わねばならないことを差し引いても、現地の大学で行われている議論のあり様を想像させてくれる、価値ある1冊である。(橋川健竜)<2015年> 目録情報 Erik R. Seeman, The Huron-Wendat Feast of the Dead: Indian-European Encounters in Early North America
–––– Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2011 ヨーロッパ人の目線に立つ史料に依拠しながら17世紀の北米先住民とヨーロッパ人の交流を描くことは、決して容易ではない。本書はカナダを舞台に、葬送儀礼という独自のテーマを設定してこの課題に迫った、興味深い研究である。 ヒューロン(ウェンダ)族の村落に住み込んで先住民言語を学んだジャン・ド・ブレブフらイエズス会士は、ヨーロッパ由来の伝染病で多数の先住民が命を落とす中、彼らを敵視する伝統派の先住民と対立しながら、 死ぬ間際の先住民に改宗儀式を施し、布教を進めた。カトリックを絶対視するブレブフはしかし1636年、ヒューロン族の儀礼「死者の祭り」を、熱心に観察して記録した。村落の死者の遺骸を掘り起こし、遺骨を集めて、 改めて集合的に埋葬するというこの儀礼の規模の大きさに、副葬品の物量に、また先住民が遺骨を手に取る際に示した深い敬意に、彼は驚嘆したのである。 カトリック教会は遺骨を聖遺物として崇拝することがあり、先住民とブレブフには意外な共通点があったのだ。1947年に行われた発掘調査とその後の遺骨の分析によれば、この時の「死者の祭り」では少なくとも681人が埋葬されていた。 ブレブフは後にヒューロン村落がイロコイ五族の襲撃によって崩壊した際に捕虜となり、殉教を理想視していた彼は、拷問を慫慂として受け、死ぬ。彼の剛毅を評価した拷問者たちは、それを我が物にしようと彼の心臓を食した。 1920年代にブレブフの頭蓋骨は半分がケベックの「殉教者の聖堂」に安置され、今日もカトリック信者の崇拝の対象になっている。また発掘調査で掘り出された遺骨は1999年、ヒューロン族の末裔たちの運動を受けて彼らに返還され、 「死者の祭り」が行われた同じ場所に再度埋葬されたという。(橋川健竜)<2014年> 目録情報 Maria Nugent, Botany Bay: Where Histories Meet
–––– Crows Nest: Allen & Unwin, 2005 ジェイムズ・クックが1770年にオーストラリア大陸で初めて投錨したボタニー・ベイは、オーストラリアという国の起点とされてきた。入植者の歴史だけがオーストラリア正史になっていくのを予行演習するかのごとく、 先住民アボリジナルは1770年にはクックたちとの接触を回避したと記録されている。しかし後の時代にボタニー・ベイに住み着いて故郷としたアボリジナル住民は、ボタニー・ベイに国の誕生と発展を見出す発想を時に拒絶し、 時に独自の記憶でそれを加工し、彼らなりの歴史理解を育んできた。著者は観光論、空間論、文化財保護論、社会運動史など多彩な分析を駆使して、アボリジナルが19世紀末期から提示し続けた独自のボタニー・ベイ史に迫っていて、 その分析の細やかさには驚かされる。たとえば1930年代にボタニー・ベイが観光地になると、アボリジナル住民は白人観光客向けの土産物としてブーメランを作って販売した。 あるブーメランにはクック到来の図像が描かれたが、「ボタニー・ベイ」でなく、入り江北側を指す彼らの語彙「ゴーリワール」が記されていた。先住民性の表象たるブーメランは彼らから見た歴史をも発していたのである。 その後20世紀末期以来、オーストラリアではアボリジナルに対する一定の配慮が見られる。クック到来が再演される時には、ボタニー・ベイは「出会いの場」と位置づけられた。 2000年のシドニー・オリンピックの際にここで行われた舞踏パフォーマンスは「ティーバーグール」と先住民語で名づけられ、アボリジナルの歌手が出演した。 だが著者はこうした配慮と、アボリジナルが社会の下層に置かれる現実との落差にも気を配っている。どの記憶が歴史を構成していくのかという、歴史学が注目する問題に一石を投じる研究である。(橋川健竜)<2014年> 目録情報 Stephen J. Hornsby, British Atlantic, American Frontier: Spaces of Power in Early Modern British America
–––– Hanover: University Press of New England, 2005 本書は大西洋史の見地から、北米大陸東半分とカリブ海の17・18世紀史を俯瞰して比較対照する歴史地理学研究である。カナダ研究の先駆者ハロルド・イニスのステープル理論を生かしている点に特色がある。 著者によれば、ハドソン湾、ニューファンドランド、またバルバドスやジャマイカは、ロンドンやイギリス南西部の有力商人に発して北米に延びる商業ネットワークと、それと並行するイギリス正規軍の存在が支える「イギリス系大西洋」の地域であり、 その経済活動はステープルの供給に特化していて収益はイギリスに吸い上げられる。住民人口の階層差が大きく、英国国教会が支配的であるなど権威主義的であり、また都市化の程度が低い。 これと対比されるのが、「農業フロンティア」地域である。ここではイギリス軍の存在が希薄なほか、植民地建設初期の間にイギリスの有力商人の支配力が弱まり、現地の商業エリート層が出現して経済活動の収益を植民地にとどめおく。 その後宗教を含め多様な文化的背景をもつ白人入植者が流入して中間層が中心の社会が作られ、数多くの作物を栽培する農業が展開する。それは多様な製造業・サービス業を発展させて、都市の成長が促されるという。 後にアメリカ合衆国となる13植民地は、サウスカロライナを部分的な例外として、この類型に該当すると著者は主張し、カナダ各地ではアメリカ独立に伴うロイヤリストの流入後も「イギリス系大西洋」の特質が維持されたと述べて本書を結ぶ。 読者は多数の地図と写真に加え、本書の大胆な整理から、17・18世紀史を包括的にとらえる着想を多く得られるだろう。(橋川健竜)<2014年> 目録情報 Anna Clark and Paul Ashton, eds., Australian History Now
–––– Sydney: Newsouth, 2013 著名歴史家によるものを含め17本のエッセイからなる本書は、オーストラリア史に強い興味を持たない人でも楽しめ、考えさせられる一冊である。大学の外における歴史の扱われ方を論じる章が、特に興味深く読める。 歴史的建造物の指定をめぐる指針の変化を論じる章があり、地域住民が地元の博物館の管理や史跡の案内などに積極的に参加する様子を紹介する章がある。 いかなる編集を経て歴史学の研究成果がテレビのドキュメンタリー番組になるか、苦労とやりがいを語る章もある。本書にオーストラリア史各分野の研究動向整理と重要文献の一覧を期待すると、むしろ拍子抜けするだろう。 アボリジナル史や女性史が出現した背景を振り返る章や、環境史やトランスナショナル史など新しい分野の可能性を語る章もあり、それぞれ読み応えがあるが、本書の目的は、歴史をめぐる今日のさまざまな「実践」について考えることにある。 本書の背景には、いわゆる「歴史戦争」がある。20世紀末期、学問的歴史研究を恣意的であるとする批判が現れて、政治問題化してオーストラリアを揺るがした。 博物館や教育界にかなりの余波が及んだが、今日では、そうした批判の眼目は、学問的厳密性のあり方を議論するより、保守的な愛国主義を強く表明することのほうにあったとされている。 だが、学問的には不毛だったこの論争を念頭に通読すると、本書がむしろ前向きな展望を示唆していることが印象に残る。学問的に厳密であることに安住せず、歴史学が歴史に関係する社会の諸側面へとその視野を広げるなら、 手を取り合える相手は多い、というメッセージが浮かび上がってくるのだ。歴史を専攻する博士課程の学生に、専門地域を問わず勧めたい一冊である。(橋川健竜)<2014年> 目録情報 Stuart MacIntyre, ed., The Historian’s Conscience: Australian Historians on the Ethics of History
–––– Melbourne: Melbourne University Press, 2004 1990年代以降、多くの国で学界の外から歴史学に対して、政治運動化した強い批判が浴びせられた。 この現象のオーストラリア版は「歴史戦争」といい、主に先住民アボリジナルの歴史をどう書くかをめぐって2000年代初めにかけて展開した。本書はそれを踏まえて、歴史研究者13名が歴史学の拠って立つ倫理についてコメントしたエッセイ集である。 多くのエッセイが「歴史戦争」の論点に応答している。この論争の論点のひとつに、歴史研究者は研究対象に対して距離をとり、それを冷静な記述で示さねばならない、という見解があるが、 本書では、母性主義の立場で行動した女性運動活動家を取り上げた史家が、母性主義に反発する現代の女性運動家から批判された経験を振り返っている。オーストラリア国立博物館の顧問を務めた史家は、 博物館は国を称えると同時に来場者に挑戦する、という立場を維持することの苦労を語る。アメリカの奴隷植民地を研究する史家は、現地の博物館が試みた黒人奴隷の競売の「再演」を例に、論争的なトピックも、 人々の未来への意志を強めさせるような歴史の語りに組み入れうると論じる。 その他のエッセイも味わい深い。人類学的分析で一世を風靡した史家が語るのは、18世紀の原史料や閲覧の難しいアボリジナルの裁判史料に触れて、活字版では見出しえなかった論点を発掘した経験である。 物語的な叙述に挑戦したある史家は、出版社から史料に基づかないプロットの追加を提案されて当惑し、また引用文が史料に基づいていないかのように紹介する書評が出たと残念がる。 ナショナリズムが惹起する困難を解決する手段として、人類史という枠組みを提唱するエッセイもある。刊行後10年近く立つが、現代オーストラリアに興味を持つ人はもちろん、歴史学を学ぶ人にとっても、一読に値する一冊である。(橋川健竜)<2014年> 目録情報 Paul Giles, The Global Remapping of American Literature
–––– Princeton University Press, 2011 アメリカ文学の内容が英語文学から英語圏文学に拡大し、さらには多言語文学へと拡大しつつある現在、アメリカ文学をいかなる視点から読みまとめれば意義ある議論ができるのかという問題は、ひとり文学研究者のみならず、 アメリカ研究に携わる者全員が共有すべき問題になりつつある。そうしたアメリカ文学を解釈する拠枠の組み替えに以前から深い関心を寄せ、自らの視点の刷新を求めるがごとく、 ケンブリッジ大学からシドニー大学へと研究の拠点を移したポール・ジャイルズの著した本書は、Transatlantic Insurrections: British Culture and the Formation of American Literature, 1730-1860 (University of Pennsylvania Press, 2001), やVirtual Americas: Transnational Fictions and the Transatlantic Imaginary (Duke University Press, 2002 )ともに、アメリカ文学を国境にとらわれずに読み解く魅力を伝える、きわめてスリリングな研究書である。 しかも、上記2作品がトランスナショナルを一つの鍵言葉にしながらも、依然として大西洋世界を検討の中心に据えがちであったのに対し、太平洋世界を含めた全世界にひろがるアメリカの文学的想像力が本書の検討課題となる。 15世紀ヨーロッパに始まる「新世界」への眼差しの歴史をハクリュートやコットン・マザーを引きながら説き起こし、ホーソン、メルヴィルらのキャノンに触れ、モダニストやミニマリストの空間表象、 スナイダーやル・グィンにみる太平洋を横断する世界観にまで説き至るジャイルズの議論は、作品群を括る視点の大きさと斬新さで読者をおおいに刺激する。 Norton他の大手出版社が近年刊行するアメリカ文学のアンソロジーは、アメリカ文学研究の新潮流を様々に示唆し興味深い。しかしさらにその一つ先を進もうと目論むジャイルズのアメリカ文学論には、歴史学・人文諸科学の研究者も学ぶところが多い。 文化地理学、カルチュラル・スタディーズなどからの理論の援用も豊かで、学際性を存在理由の一つにしてきたアメリカ研究の活きの良さを久々に感じる著書として高く評価できる。(遠藤泰生)<2012年> 目録情報 Michael Zakim and Gary J. Kornblith, eds., Capitalism Takes Command: The Social Transformation of Nineteenth-Century America
–––– Chicago: University of Chicago Press, 2012 計量的分析を推進する経済史に対して歴史学の側が距離をとり、また人種・エスニシティ・ジェンダーを重視していくにつれ、経済の変化は19世紀アメリカ史研究の対象から外れがちになった。
たとえば労働者階級形成史はかつて、全国的市場の形成や技術革新、企業経営の革新といった経済史の論点と密接につながっていたが、今日ではしばしば、「白人性」を研究するための領域となっている。
これに対して本書は、19世紀に「資本主義」が社会を再編成したと主張して着目を促す、興味深い論文集である。議論の中心は社会史・文化史が扱ってこなかった資金調達のネットワーク・資本の形成とその担い手の分析に置かれていて、
著名研究者と有力な若手・中堅の研究者が力作10篇を寄稿している。 Paul W. Mapp, The Elusive West and the Contest for Empire, 1713-1763
–––– Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2011 北米大陸を語ることで世界史を語れる研究を行うことは、アメリカ史研究者に課せられた容易ならざる課題の一つである。本書は地球全体に迫る広大な空間、複数の学問分野と英西仏の三言語、汗牛充棟の研究文献を縫い合わせてこの課題に応じた、驚くべき書である。 Olivier Zunz, Philanthropy in America: A History
–––– Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2012 アメリカ社会においてフィランソロピー(博愛的な慈善活動)の果たす役割は非常に大きく、またその活動のあり方はきわめて多様である。 社会改良のための研究や教育の推進、貧困の撲滅、人権擁護や国内外の人道的危機への対応など、フィランソロピーの活動領域は19世紀末以降拡大し続けてきた。 活動を担う組織も、赤十字や救世軍など主として市民の寄付に頼るものから、カーネギー財団やロックフェラー財団など20世紀初頭の実業界の巨頭によって設立されたもの、 そしてビル・ゲイツやジョージ・ソロスなど今日の大富豪が個人財産をつぎ込んで展開するものなど多岐に渡っている。アメリカが「フィランソロピー先進国」であることは、内外で広く認知されていると言えるだろう。 『アメリカにおけるフィランソロピー:その歴史』と題された本書は、フィランソロピーがアメリカ社会の中で果たしてきた役割を歴史的文脈に位置づけ、その特徴と影響力を探るものである。 フィランソロピーはアメリカの民主主義の発展にいかなる影響を与えたのか、非営利セクターの誕生は、国家とフィランソロピーとの間にどのような関係があったことを示しているのか。 本書では、フィランソロピーが共通善の推進を目的としながらも、しばしば個別的な政治的アジェンダの追求や、宗教的活動と結びついてきた様子が叙述されている。 そこから浮かび上がるのは、フィランソロピーと自己利益、あるいは政治、宗教、社会改革との関係が、一筋縄ではない複雑さを伴っていたことである。 それでも著者によれば、フィランソロピーは社会正義や共同体の理想を打ち出すことで、国内外における経済・社会的な改革を牽引する役割を果たしてきた。 さらに、寄付行為などを通じて一般市民が社会への関与を強める機会を提供し、アメリカの民主主義を活性化してきたところに、フィランソロピーの最大の重要性が認められると結論づけている。 著者のオリヴィエ・ザンズはヴァージニア大学歴史学科コモンウェルス講座教授。Making America Corporate (University of Chicago Press, 1990)、Why the American Century? (University of Chicago Press, 1998) (邦訳『アメリカの世紀』(有賀貞・西崎文子訳、刀水書房、2005)などで知られる。20世紀アメリカの社会史の他、トクヴィル研究にも造詣が深く、トクヴィル協会の会長もつとめた。(西崎文子)<2012年> 目録情報 Gilles Havard, The Great Peace of Montreal of 1701: French-Native Diplomacy in the Seventeenth Century, trans. Phyllis Aronoff and Howard Scott
–––– Montreal & Kingston: McGill-Queens University Press, 2001 初期カナダにおける先住民諸部族と入植者社会との交渉は、毛皮交易はもちろん、政治外交の領域でも不可欠の主題である。ヌーヴェル・フランスは、五大湖南部を勢力圏とするイロコイ族と、17世紀を通して敵対関係にあった。 特に世紀後半の直接的な衝突のインパクトは大きく、同植民地では軍と民兵隊が社会の枢要な組織になっていく。この対立に終止符を打った1701年の和平は、18世紀にかけてのヌーヴェル・フランスと英領植民地の対立を考える上でも無視できない。 フランスの文書館に所蔵された史料とエスノヒストリーの知見をもって、この和平をニュアンス豊かに、かつコンパクトに論じたのが本書である。 本英語版は、著者が1992年に弱冠25歳で発表したフランス語版を基に、その後の研究も取り込んで加筆した決定版である。ヒューロン―ペタン族やオダワ族など、イロコイ族以外の部族が1701年の和平条約に参加したことに注目する本書は、 和平交渉に先立つ時期に五大湖以北・北西部の諸部族がイロコイ族の抑え込みに果たした役割や、彼らの和平交渉への参加(参加した部族名、さらに部族内の勢力を特定している)、 イロコイ族内部の親仏派・親英派・中立派の描写など、先住民外交の機微を明らかにしている。一貫して強調されているのは先住民側の主体性の発揮で、交渉は先住民の儀礼にのっとって行われ、条約文自体も、 ヨーロッパ外交文書の形式と、先住民流の交渉の形式の双方が条約文の構成に流れ込んでいたという。署名代わりに記された38ないし39の部族マークも含め、条約文の原史料(複製)が図版掲載されていて、読者は原史料によって著者の議論を検証することができる (補遺に英訳もある)。 大きな主題を扱うだけに、本書の個々の論点には異論の余地もありうるだろう。だが、和平の過大評価を戒めつつ、各集団にとっての意義を論じる筆致には好感が持てる。 また先行研究をテキパキと整理し、論点をくっきり浮かび上がらせ解釈する小気味良い文章は、翻訳でも著者の頭脳の冴えを存分に感じさせる。先住民の行動パターンにかんする説明はそのよい例で、 支配欲や経済利害といった還元主義的な解釈を排し、先住民外交における贈り物の重要性、個々の先住民が戦闘・武勲に価値を見出していたこと、部族社会は国家機構ではなく、構成員を統制する強制力を持たなかったこと、 そして部族内で死者が出ると戦争で他部族から捕虜を取って部族人口の減少を補うという慣習の存在(それゆえ捕虜の返還は困難を極め、和平交渉を難しくした)など、文化的背景への言及が大変効果的である。 17〜18世紀先住民―入植者関係史について多くの知見を与えてくれる一冊であり、アメリカ史研究者にも一読を薦めたい。(橋川健竜)<2012年> 目録情報 |