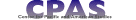
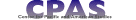

|
脱工業化社会における歴史と記憶 マイケル・フリッシュセミナー参加記 北脇 実千代 2001年5月31日、ニューヨーク州立大学バッファロー校アメリカ研究科のマイケル・フリッシュ教授による講演が行われた。フリッシュ氏は、1999−2000年のASA会長であり、本講演は日本アメリカ学会の基調講演に先駆けてのものとなった。"Communities, Memories, and Contested Uses of History"と題されたその講演において、氏は脱工業化社会におけるパブリック・ヒストリーの問題を主に取り上げた。文化戦争(cultural war)やPC論争、最近では映画『パール・ハーバー』をめぐる議論が示唆するように、近年「歴史」は常に論争の的である。フリッシュ氏は、そのような状況をふまえて、コミュニティにおける歴史と記憶の問題、特に脱工業化時代を迎えてそれぞれのコミュニティが工業化時代の遺産といかに向き合うかという問題を扱った。 まず始めに、フリッシュ氏は、工場跡地の再利用計画や旧工員のオーラル・ヒストリー・プロジェクトなどを通して、工業都市だった時代の遺産に関わる人々を5つの「部隊」にたとえた。第一の「部隊」は、自らの生活やコミュニティそのものが「過去の遺産」となってしまった労働者や労働組合。第二は、自らの歴史に対する興味や関心をより広い公的な領域に還元しようとする歴史学者たち。第三は、遺産を旅行者向けに活用することを試みるビジネス集団。第四は、遺産を通して労働者の体験や価値観に焦点を当てようとする活動家たち。そして第五は、公的資金を利用しながら工業都市時代の遺産を利用しようとする市や州、連邦政府である。フリッシュ氏は、このような構成員から成るそれぞれの「部隊」が、過去を称えるという目的から遺産に関わるものの、思惑の違いから衝突していく状況を「鉄道の町」だったオハイオ州ライマの例などを挙げながら説明した。 続いてフリッシュ氏は、以上のような工業化時代の歴史と記憶の活用をめぐる摩擦を、脱工業化という文脈の中で捉え直す。脱工業化がひとつの発展段階として当然視されている中で、人々はその変化に対応していかなければならない。その対応をめぐる混乱が「部隊」の衝突にもなるわけだが、結局のところそれは「歴史」を問い直すことにもつながる。自分たちが生きてきた工業化時代を「歴史」として捉えなければいけなくなるからだ。人々を取り囲む環境が大きく変化していく中で「歴史」が意味するものは何か。人々は「歴史」にどう対処するべきなのか。歴史のどの部分を重視し、記憶していくかは人々の取捨選択に拠る所が大きい。過去を志向するか、未来を志向するか、それによっても歴史の捉え方は変わってくる。フリッシュ氏は、そのような緊張感を、自身が長年居住するニューヨーク州バッファロー市郊外の橋のデザインをめぐる論争に触れながら言及していった。 このように「歴史」が問い直される中で、オーラル・ヒストリーはどのような意義を持つのか。フリッシュ氏の論点はそこへ移っていく。ここで氏は、自身が関わったプロジェクトをスライドで紹介した。鉄鋼労働者を20年近く追ったそのプロジェクトは、個々の労働者にとって、もしくはコミュニティにとって、脱工業化とは何なのか、そして「歴史」とは何なのかを探ったものであった。もはや鉄鋼労働者ではない彼(彼女)らの過去と現在を比較しつつ、職場と家庭での両方の姿を追い、一枚岩でない「労働者の生活」を明らかにする。この点において、氏は「歴史」の複雑性とそれを呈示するオーラル・ヒストリーの可能性を指摘したといえる。これは同時に、誰の歴史を記憶するべきなのかというパブリック・ヒストリーの問題を示唆したものでもあった。 最後にフリッシュ氏は1901年にバッファローで開催されたパン・アメリカン博覧会の様子をウェブ上で再現するという現在進行中のプロジェクトを紹介したが、これは「歴史」を現在の視点で問い直し、さらには「歴史」と未来とのつながりをも意識したプロジェクトだといえよう。総じて、本講演は、パブリック・ヒストリーをめぐる多様なせめぎあいに触れながら、「歴史」の意味とその複雑性を指摘した意義深いものであった。 (きたわき みちよ:津田塾大学大学院) |
