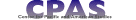
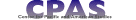

|
『北極光』―映画にみる樺太アイデンティティ テッサ・モーリス=スズキセミナー参加記 澁谷 智子 去る1月31日、テッサ・モーリス=スズキ氏の講演が行なわれた。会場は、椅子を入れても入れても足りなくなるほどの人で大盛況だった。集まった人々の専門も、アメリカ研究だけではなく、近代日本や北洋水産業などと、多様であった。そのため、英語への慣れや樺太の知識についてはかなりの個人差が見られたが、とりあえず講演は英語で、説明を補うような形で進められた。 まず、モーリス=スズキ氏は、「外地」樺太が、入植者によって開拓された土地(settler's colony)であったことを強調した。そして、そのような場所のアイデンティティには、パラドクスとも言うべき二つの側面が見られたことを指摘した。すなわち、郷土に帰属する土地という意識と、異国情緒漂うフロンティア(辺境)という意識である。言うまでもなく樺太は、数々の条約によって日本になったりロシアになったりしてきた地域だが、日露戦争後から第二次世界大戦終戦にかけての時期は、日本の一部としての側面と、アイヌやウィルタなどの先住民族が住むエキゾチックな土地という側面が、並存していた。 後半では、特に文学や映画に絞った樺太表象が論じられ、具体的な作品として、戦前に作られた映画『北極光』が取り上げられた。この作品では、樺太開拓の途中に殺された父を持つ主人公が、父の遺志を継いで樺太に渡り、さまざまな犠牲を払いながら国家事業としての鉄道建設をやり遂げるまでが描かれている。樺太の植民を奨励する政府の思惑もあって作られたこの映画では、日本国発展のために己を捧げながら開拓に燃える英雄たちと、樺太の資源を狙う悪徳資本家たちが対比された。また、映画の中ではアイヌの人々も描かれた。主人公の父の親友が、アイヌの娘と結婚して「土人部落」の酋長になっていたという設定で、この酋長は村を率いて主人公の鉄道建設に協力するのである。アイヌの人々は、民族衣装を着て太鼓を打ち鳴らし、伝統的な歌を歌いながら火の周りで踊る。日本語がわかるアイヌは登場しない。一方で、歴史上、鉄道建設に加わっていたものの、中国大陸や朝鮮半島から連れてこられた人々については、映画で描かれることはなかった。多様な人々が住む樺太の現実は、ありのままに語られるのではなく、特定のイメージに沿って、語られたり語られなかったりする部分を持っていたのである。 私事になるが、筆者の祖母は樺太育ちである。私は子供の頃から、ニシン漁の賑わいやスズランの咲き乱れる美しい丘、干すそばからバリバリに凍ってしまう洗濯物などについて聞かされたが、祖母の話では、樺太が日本の延長であることは、疑いのないものとされていた。祖母が住んでいたのは「ロ助小屋」と呼ばれる丸太小屋であったが、それでもロシアは単なる背景に沈み、祖母の現実感としてあったのは、「きちんとした」家の子と漁師の子というような階層や、進んでいる東京と田舎の樺太という、地方と都市の格差であった。一入植者の娘として育った祖母の生活では、朝鮮半島から連れて来られた人々はおろか、アイヌやロシア人とさえも、直接に触れ合ったり意識したりすることがなかったのだと思う。そのような生活者の意識がある一方で、政府関係者などは樺太の異民族を意識して同化政策を進めていた。また、それとは別のレベルで、映画や文学作品で描かれる樺太像があった。このように、樺太のアイデンティティはさまざまな重層性を持っていたわけである。モーリス=スズキ氏の講演は、樺太のその複雑なアイデンティティ構成を考えさせてくれる上でも、刺激的であった。最後に、筆者に映画『北極光』のコピーを快く送って下さったモーリス=スズキ氏にお礼を申し上げ、今後のさらなるご活躍をお祈りしたいと思う。 (しぶやともこ:東京大学大学院) |
