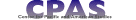

|
"Rights Consciousness and 'The Labor Question' " リヒテンシュタイン研究会参加記 梅崎 透 ニューディール期以降の数十年間を,一貫性をもった一つの時代としてとらえる見方がある。労働運動がある程度の成功をおさめたとほぼ同時に'labor question'が急速にその重要性を失ったのはなぜか。1930 年代には階級的不平等に焦点を当てていたリベラリズムが,1960 年代には人種的不平等へと焦点をうつしたのはなぜか。これら二つの問いはニューディール期以降の合州国史を把握するあたって中心的な課題の一つとなっている。1998 年10 月20 日にヴァージニア大学歴史学部のネルソン・リヒテンシュタイン氏がおこなった講演は,まさにこの課題に正面から取り組むものであった。 リヒテンシュタイン氏はまず,20 世紀を特徴づけるもっともラディカルな立法として,1935年のワグナー法と,1964 年の公民権法をあげた。ワグナー法は,'labor question'への答えとして制定されたものであった。一般に'labor question'とは,単に労働と資本の関係を改善するのみでなく,搾取,社会的不平等など,民主的な社会関係への脅威を排除することを意図して用いられることばである。ワグナー法は労働者が自主管理に基づく団体交渉を通じて,労働環境だけでなく,社会全体のアジェンダに対して声を発する道筋を保証したのだった。ここに「産業民主主義」が具現されたのである。しかしながら,'labor question' は第二次世界大戦後,急速にその問題の重要性を失い,団体交渉という手段も徐々に衰退した。このことは産業民主主義がもはや役割を終えたことを示していた。リヒテンシュタイン氏はその原因として,産業民主主義が個人ではなく,組織化された組合集団を単位としていた点,そしてその対象から黒人や女性をはじめとする多くのマイノリティが除外されていた点をあげた。 一方,1964 年の公民権法は,人種,性にかかわらず,個人を単位として,その市民としての権利を保障するものとして制定された。以後,さまざまな立法が個々人の権利を保護するものとしてなされてきた。リヒテンシュタイン氏は,ここにおいてアメリカのリベラリズムがその焦点を,集合行為(ここでは労働組合運動)から個人の権利保護へとシフトしたと指摘した。そしてその結果,ジェンダーによる差別等を含む,立法や行政の保護が及ばない新たな問題に対して,労働者が声をあげる手段を失い,その権利を守るシステムが形式主義に陥る恐れがあることを指摘した。さらに,権利侵害の解決にあたることができるのは国家機関のみであるが,その解決能力にも限界があることが指摘された。 セミナーでは,報告者に対し,同大学のアイリーン・ボリス氏が女性史の立場からコメントし,議論を補った。また,フロアからはニューディール期以降の南部における労使関係についての質問などがなされ,活発に議論された。 団体交渉を軸とする,いわゆる「ニューディール型労使関係」を合州国において唯一可能な労使関係と考え,その連続性を考察する研究は1980 年代の著しい労使関係の変化をうけて盛んに行われてきた。リヒテンシュタイン氏の報告は,自身も与するこの観点に,個人の権利意識の高揚というもう一つの流れに対する考察を加えることによって,リベラリズムそのもののシフトというダイナミズムをとらえた点におもしろさがあった。ただ,報告者が40 年代の労使関係を専門としているだけに,そのシフト過程への踏み込んだ言及が欲しいところであった。 一般に,ニューディール期以降の団体交渉を軸とした労使関係を考察する議論に対しては,国家による労使関係への干渉の是非そのものを問うていないとの批判がある。また,団体交渉の消滅は決して社会運動の全般の消滅を意味しているわけでもない。むしろ職場以外の場では,他の集合行為との相互作用をともなって民主的な社会関係創出の努力が絶えず行われてきた。では,すべての個人の権利保護が国家の「解決能力」を超えるとき,集合行為は,いかなる形で職場の「正常さ」を問うことができるのか。ニューディール期以降の合州国おけるリベラリズムのシフトという大きな流れのなかで集合行為のあり方を問うリヒテンシュタイン氏の議論は,1960 年代の社会運動を歴史的に位置づけることを目指す自己の研究においても大変興味深いものであった。 (うめざき とおる・一橋大学院) |
