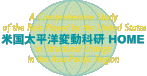文部省科学研究費補助金「特定領域研究(B)」
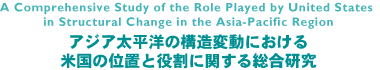
政治外交班 1998年度活動概要・研究会議事録
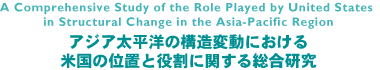
1998年度活動概要
本年度の活動は、主としてアメリカの政府文献、公文書、議会の報告書などの資料収集、そしてさまざまな地域の専門家を招いての研究会の開催が主なものであった。研究会は、現在まで、国分良成慶應義塾大学教授による「中国をめぐる諸問題」という報告および参加者による討論(1998年11月28日)、渡邊昭夫青山学院大学教授による「最近のアジア太平洋地域の情勢と日米関係 − APECを中心に」という報告および参加者による討論(1999年1月25日)、高野紀元外務省研修所所長による「アジア太平洋の現状」という報告および参加者による討論(1999年2月5日)を開催した。また、代表者の五十嵐が1999年1月2日よりアメリカ合衆国に短期の出張を行った。
1998年度研究会議事録
凡例:1)会議あるいは報告タイトル、2)報告者、3)日時、 4)場所、5)コメンテイターなど、6)会議の概要
第1回
1)中国をめぐる諸問題
2)国分良成(慶応義塾大学教授)
3)98年11月28日
4)学士会館分館
6)概要:
国分教授は、現在の米中関係、日中関係ならびに、それらと中国国内情勢との連関について報告を行った。クリントン訪中時における、米中の戦略的パートナーシップの形成は、アメリカの対ロシア関係の改善と日米安保のガイドラインが、中国にとっては一種の中国方位網と認識されたため、その環境を改善するためになされたもので、ロシアとの接近や、日中関係とあわせて理解すべきだとの指摘がなされた。今回の江沢民主席の訪日については、両国関係のイメージの改善や個人的信頼関係の構築といった観点から見ると、必ずしも成功とはいえず、「歴史」と「台湾」という二つの要素が今回も阻害要因として機能したとの分析であった。すなわち、今回の江沢民主席訪日時に共同宣言に署名しなかったのも、クリントン訪中の場合と異なり、台湾問題で日本の譲歩を得られなかった江沢民主席が、その代わりの目に見える成果として歴史認識問題を取り上げたというのである。また、今後の日中関係において重要なことは、世代の変化とともに一種の構造変化が日中関係の中でできていることで、政府間同士の公式チャンネル以外のルートのなさが問題となるという指摘がなされた。これは、さまざまな人的コネクションを現在構築しつつある米中関係とは対照的だとされる。そのほか、中国経済、中国の政治体制の将来が今後の東アジアの国際環境にいかなる影響を与えるかについても、重要な指摘が多数なされた。報告のあと、参加者全員による質疑応答が活発に行われ、有意義な知見が多数得られた。
第2回
1)最近のアジア太平洋地域の情勢と日米関係−APECを中心に
2)渡辺昭夫(青山学院大学教授)
3)99年1月25日
4)学士会館分館
6)概要:
渡辺教授の報告では主に、1.APECに対するブッシュ・クリントン両米国政権の思惑(期待)2.ボゴール/大阪会議以降のAPECの「失速?」状況3.アジア経済危機のAPECへの影響、などの諸点について論じられた。ことに、2.の論点に重点がおかれ、95年の大阪行動方針および96年のマニラ行動計画で示された諸提案の批判がなされたあと、97年のヴァンクーバー会議で示された改革案に着いて検討が加えられたが、その際、97年会議自体の影の薄さが指摘された。渡辺教授は報告を通じて終始、ヴァンクーバー会議が「見えにくい」ことを強調しており、このことはAPECの「失速」のあらわれであろうかと問題提起した。APECは発足当初はアメリカの強い主導のもと、さまざまな期待と共に語られた、いわば米国中心の国際関係における花形であったが、最近はほとんど表舞台から退いてしまっている、というニュアンスが「失速」という表現には込められているようである。これに対し、五十嵐教授から、米国の対外政策の重心が貿易から金融へとシフトしたことの帰結として、貿易自由化を扱うAPECへの関心が薄らいだのであろうとの指摘がなされた。さらに、北岡教授から、イラクや北朝鮮の問題もあり、米国にとっては貿易問題どころではないのだろうとも付け加えられた。(もっともこの点については、五十嵐教授はルービン財務長官の就任以降、安全保障問題よりも金融問題の比重の方が大きいと主張した。)結局、APECはもっぱら米国主導で動いているので、米国の外交方針にしたがって存在感が増したり減ったりするのであり、当面は現状維持的傾向が続いていくであろうとの基本認識で一致した。その他にも、WTOとの関係や、宮沢構想の位置づけといった重要な論点についても、おもに米国の観点から論じられた。また、報告と直接関係はないが、日米関係・アジア・ASEANの動向に関するさまざまな論点について活発な討議が行われ、アジア・太平洋地域の情勢について多角的な視点から認識が深められた。
第3回
1)アジア太平洋の現状
2)高野紀元(外務省研修所所長)
3)99年2月5日
4)学士会館分館
6)概要:
高野所長の報告では、朝鮮半島(北朝鮮・韓国)・韓国・中国・米国に関する基本的な外交情報が、それぞれの国について、日本の外務省の立場から網羅的に概観された。また、アジア経済危機についても言及された。報告および質疑への応答では、外務省の基本的見解・解釈が示されたような印象を受けた。質疑は多様な観点からなされた。五十嵐教授からは、アジア危機や朝鮮問題が協力の契機となっているのではないかという理論的把握が提起された。とくに、アジア危機に関しては、米国の金融政策重視路線の結果、日米関係に新しい構図ができてきたのではないかという見取り図が示された。それに対して高野所長からは、結果としてそういうこともいえなくはないが、日米関係については、水面下で米国が常々要求してきたことが、(日本側のコミュニケーション不足のせいか)表面化してきただけのことであり、また、朝鮮問題についても構造的な変革・改善といった類のことではない、という見解が示された。また、米国の対北朝鮮認識に関して、湯浅・大津留両助教授から質問があった。湯浅助教授は米国の対北朝鮮姿勢が軍事行動を含めて強硬化する傾向にあるのかという疑問が提示され、また、大津留助教授からは、米国にとっての朝鮮問題は、米国本土の防衛問題という認識へと変わってきたのではないかという考えが示された。高野所長はこれらに対しては否定的な見解を示し、あわせて、日本の対北朝鮮外交は、KEDOへの援助を凍結するといったソフト路線と、軍事行動を念頭に置いたハード路線との中間あたりで柔軟に行われており、強硬方針はとらないような形で、米国への説得も含めた外交を展開して行くだろうと述べた。また、米韓関係について木宮助教授から日本との温度差が大きいとの問題提起がなされ、それに対して、韓国は米国の強硬論を抑えるかたちで、米国と共同歩調を取りつづけて行くだろうという認識で一致した。このほか、韓国軍および一般市民の対北朝鮮および日本認識について趙氏から体験談が語られたり、北岡教授から米国の対日要求について事実関係が質問されるなど、具体的な話題に事欠かなかった。
第4回
1)アジアの通過金融危機と日本
2)猪木武徳(大阪大学教授)
3)99年2月16日
4)学士会館分館
6)概要:
報告では、昨今の市場経済の特徴として、市場の短期化という現象が説明され、さらにその問題点を踏まえた上で日本に対する政策提言がなされた。市場の短期化とは主に、1.人材調達市場における視野の短期化 2.短期資本の増大(ポートフォリオの短期化)3.R&D(研究・開発)における視野の短期化の3つを指す。人材調達においては、コストやリスクを低く抑えながら短期的に利益が上げられるような能力が求められる評価システムが、短期化現象と把握されており、例として年俸制があげられた。年俸制は能力主義を明確にしたシステムとして昨今はもてはやされる傾向にあるが、リスク回避傾向や業務の質的悪化などのマイナスをももたらすことが示され、また、日本で伝統的に行われてきた年功制が、実は競争をベースとしながらも中・長期的な視野に立った評価を可能にするシステムなのであり、その利点を見逃すべきではないことが説明された。短期資本の増大は,金融危機を引き起こし経済システムに壊滅的な打撃を与えかねない元凶であるとして、アジアにおける通貨金融危機の発生もこれによるところが大きいと説明された。短期資本は、輸出指向型産業政策をとっており、直接投資を誘致する政策をとっている国家に流入しやすいと言われているが、アジアの国々はまさにその条件を満たしていたうえに、成長率が高かったために、大量の短期資本が流れ込んでいた。ところが、ドル・ペッグ制に起因する通貨高と高利子率がもたらしたバブルが主因となって短期資本が一挙に流出し、また、日本などメジャーな直接投資国が投資先をシフトしたことも重なって、アジア危機が招来されたのだという。R&Dに関しては、R&D軽視の一例としてアメリカにおける知識・技術の外注傾向があげられ、これも短期決戦型競争経済におけるリスク回避傾向の現れであり、長期的には企業が提供するモノやサービスの質的低下をもたらし、また、プロダクト・サイクルの短縮化に拍車がかかることで、視野の短期化が促進されることになるとの危惧が示された。以上のような市場の短期化傾向の分析を踏まえて、日本への政策提言として、人材調達市場における視野の中・長期化(年功制の再評価)・専門性を尊重すること(たとえば、経済戦略会議を金融の専門家を中心に構成するなど)・社会的公正や国益を確保するために専門化集団を確立すること(伝統的に官僚組織がその役割を担ってきた)・技術標準の設定に積極的に発言・関与すること、などが主唱された。